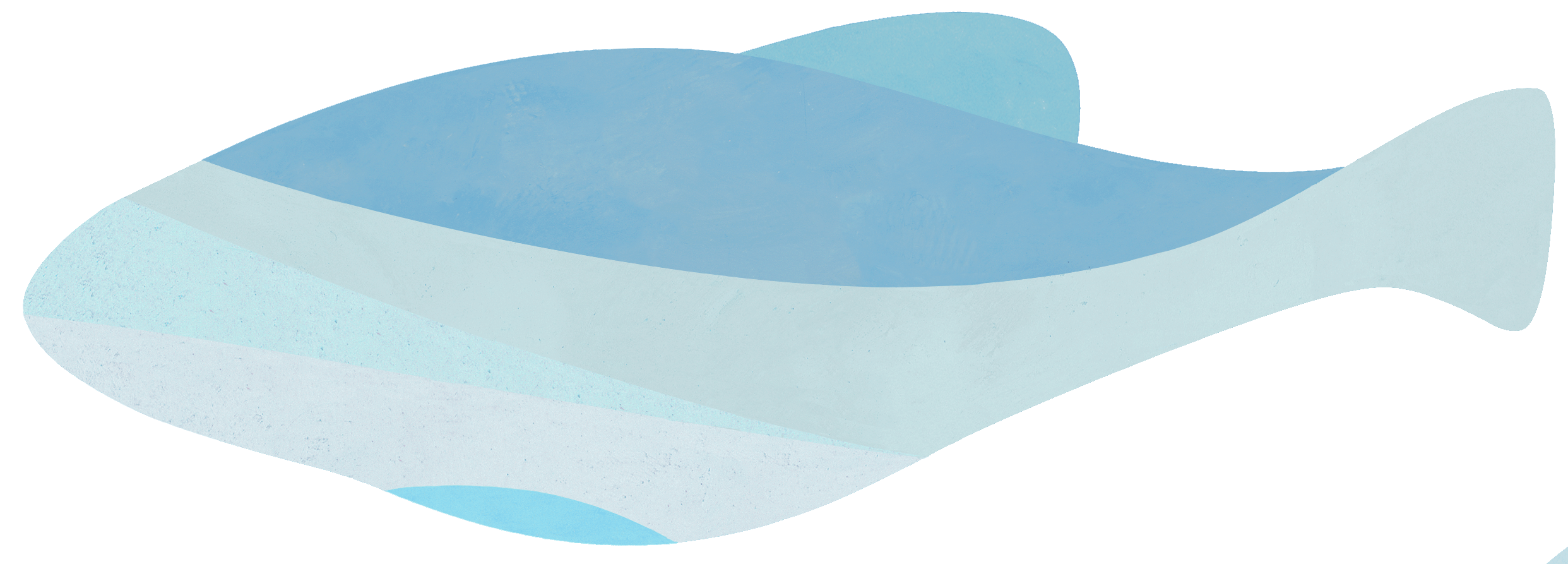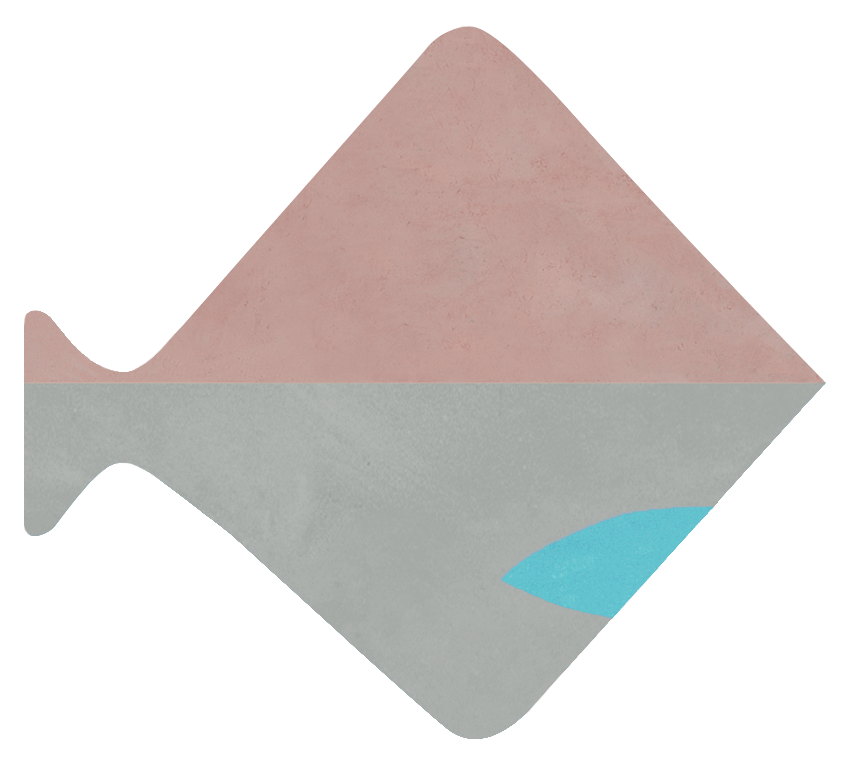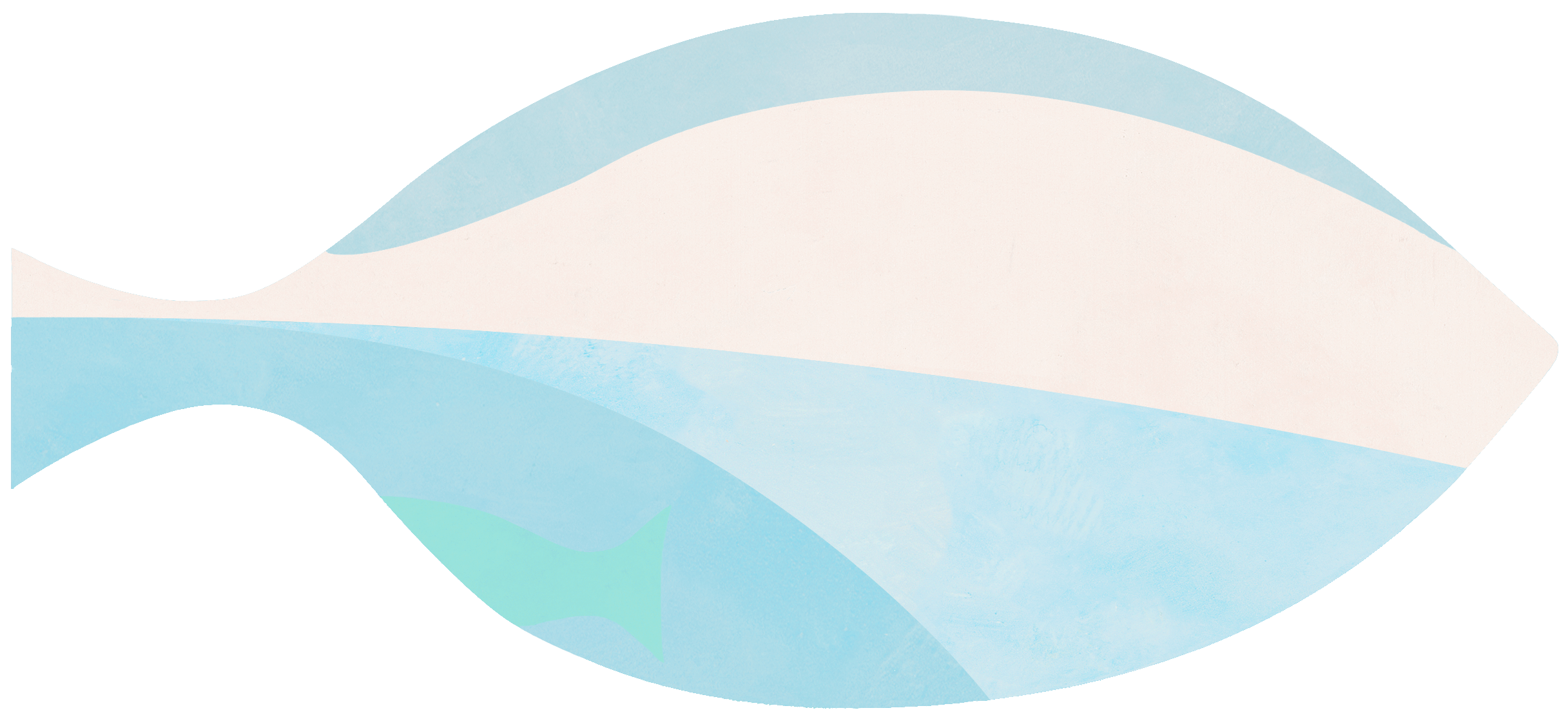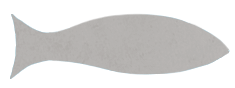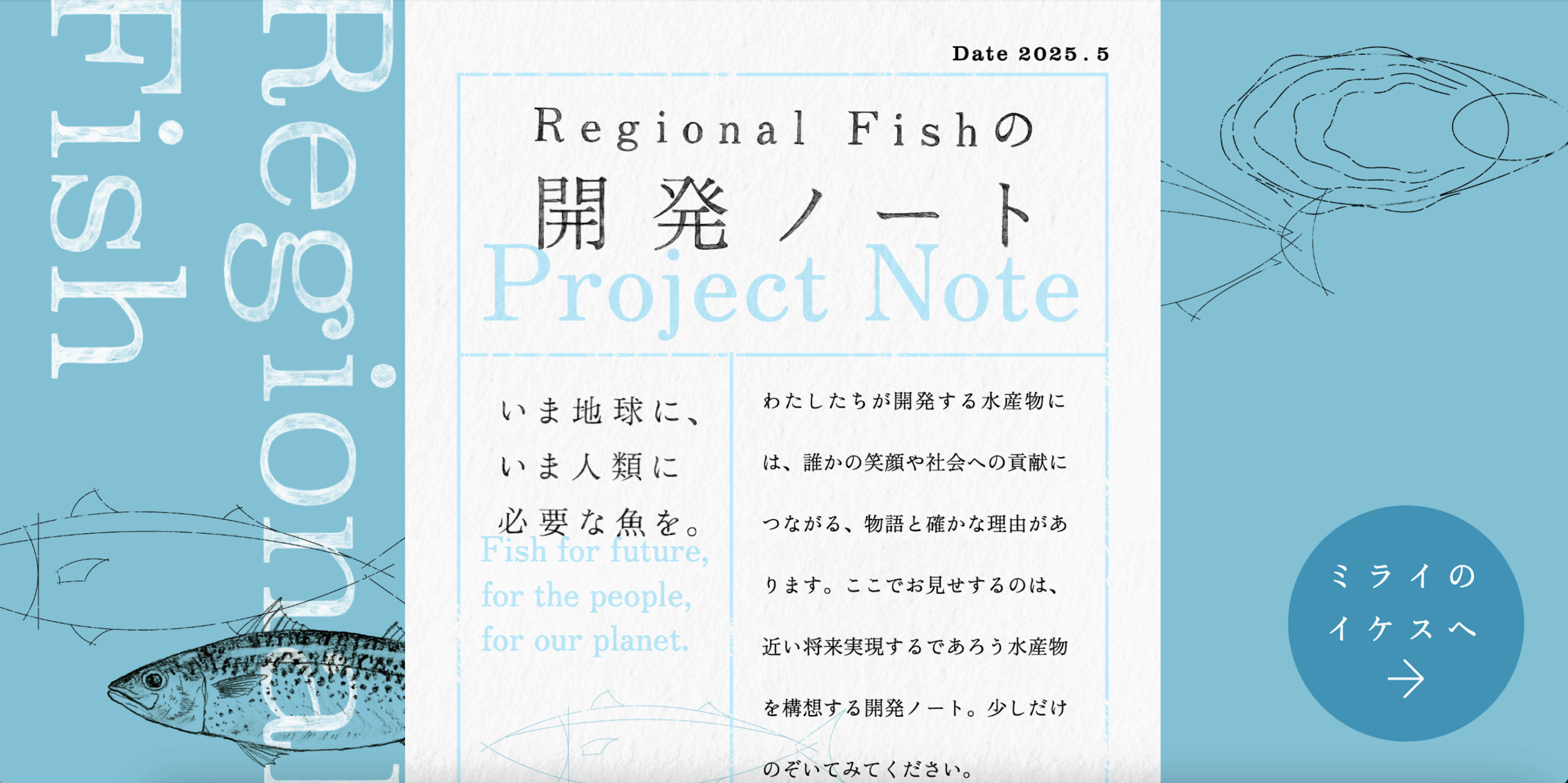命をいただく「ありがたみ」を魚に教わる
「魚はおいしいけれど、ちょっと面倒くさい」——そんな理由で、食卓に魚を出す機会が減ってはいないだろうか? 骨が多い、調理が大変、そもそも子どもが食べたがらない。そんな背景から、魚を食べる子どもが少なくなっていると言われている。
料理家の和田明日香さんも、この状況を気にかけているひとりだ。
「家で魚料理をもっと手軽につくってほしいし、子どもたちにはもっと魚を好きになってほしいですよね」
実際、和田さんの家庭では、日常的に魚料理が肉料理と同等に食卓に並ぶ。魚は肉が苦手な次女にとっては欠かせない食材だ。一方で、長男は魚があまり得意ではない。そのため、和田家の食卓には日頃から、魚と肉の2種類のおかずが用意され、それぞれが食べたいものを自由に選んでいる。

和田さんご提供
「苦手なものを無理に食べさせることはしません。食べたいものを、自分のペースで食べてくれればいいと思っています。でも、魚には骨や皮があるからこそ、『生き物の命をいただいている』ことを実感しやすい食材だと思うんです」
魚にふれることが「おいしさ」につながる
魚が苦手で普段はまったく口にしない和田さんの長男は、自分でさばいた魚だけは食べるのだという。
「父親と一緒にYouTubeを見ながらさばいてみたら、思いのほか楽しかったみたいで。まるで工作のような感覚だったようです。自分で手を動かしてつくると、やっぱりおいしさが違うんでしょうね」

そんな長男に、和田さんはある工夫をしている。週末、スーパーで子どもでもさばきやすそうな魚を見つけたら買い、「あとはよろしくね!」と長男に託すのだ。
「丸ごとの魚を、自分で食べられる形にする。この体験が大きな達成感につながっているようです。自分でできた!という実感が、自己肯定感も高めてくれるんですよね」

一方、肉が苦手で魚好きな次女の好物は、なんとホタルイカ!
「食べたいなら手伝ってね」と声をかけると、自ら下ごしらえを買って出る。目玉や口を取り、背骨を抜く……。大人でも手間に感じる作業だが、「おいしいホタルイカを食べたい!」という思いで、何十匹も夢中になって下ごしらえをするという。

『楽ありゃ苦もある地味ごはん。』(主婦の友社)より
「魚をさばいて、下ごしらえをして、口にする——この一連のプロセスを経験できるのは、魚の調理ならでは。命をいただく実感が湧くし、たくましさにもつながる気がします」
魚はシンプルな塩焼きがいちばん

『楽ありゃ苦もある地味ごはん。』(主婦の友社)より
魚料理のレパートリーに悩む人は多いが、そんな人たちに和田さんがいつも話すのは、「魚こそシンプルな料理がいちばん」ということだとか。
肉と違い、魚は時期によって旬が違う。同じ塩焼きでも魚の種類が変われば、味も香りも全く変わってくる。何か凝ったものを、と思うから料理をすることが面倒になるけれど、シンプルに素材の味を楽しめばいいのだ。「手間のかからない塩焼きやお刺身で食べるのが、きっといちばんおいしいはずです」。
「でも毎日、お刺身や塩焼きだと飽きちゃうなら、普段の料理をそのまま魚に置き換えてみるのがおすすめ」と和田さん。たとえばフライパンで魚の切り身を焼いて、豚肉の生姜焼きと同じように味付ける。鶏の唐揚げは白身魚の揚げ物にアレンジ! そう考えると、魚を調理する面倒さもどんどん薄れてくる。
ちなみに和田家で人気の魚料理は、「ガーリックバター焼き」!
「これは、どんな魚でも絶対においしくなります!」と和田さんが太鼓判を押す絶品レシピ。調理をしていると、そのおいしそうな香りにつられ、家族が入れ代わり立ち代わりキッチンをのぞきにくるほどだという。

『楽ありゃ苦もある地味ごはん。』(主婦の友社)より
フライパンに油とニンニクを入れて火にかけ、ニンニクの香りが立ってきたら、切り身を立てるようにして皮目をじっくり焼く。皮目がカリカリになったら、身に軽く焼き目がつくくらいにサッと焼く。しょうゆを回しかけて最後にバターを入れれば完成! 「さくっと作れて、間違いない味にできあがります」と和田さん。
魚をおいしく食べる選択肢はひとつではない

気候の変化など、水産業を取り巻く環境は日々変化している。そんな中、和田さんは、おいしいお魚をこれからも食べ続けられるように、頭を柔らかくして学ぶ姿勢も必要と感じている。
「以前、長崎大学でブリの養殖を研究している先生とお話する機会がありました。『天然物は海で何を食べているかわからない。そう考えると安全性をしっかり管理している養殖のほうが安心といえることもある』と教えていただき、それは確かにそうだなと納得しました」
環境の変化による漁獲量の減少や担い手である漁師の高齢化などは、水産業にとって深刻な問題だが、その解決策のひとつが品種改良だ。改めて考えてみると、普段私たちが食べている肉や野菜はよりおいしく多くの人が食べられるように品種改良されているものばかりだということに気づく。しかし、なぜか魚等の水産物だけ、品種改良がなかなか進んでいない。
そこで今回の取材に際して、和田さんに品種改良して身が肉厚になった鯛を使った鯛めしを実際に食べていただき感想を聞いてみた。

「手軽にすぐに食べられるセットで、シンプルな鯛とアラ出汁の味がすごくおいしくてびっくりしました。土鍋で炊いていただきましたが、加熱しても鯛の身がふわふわで、食べごたえがあって大満足! 子どもたちも、レミさん(義母で料理愛好家の平野レミ)も喜んで食べていました」
味への満足度のほかに、和田さんが驚いたのは、普段私たちが食べている鯛は食べられる部分が少なく、6割が捨てられているということだ。
「たしかに鯛は頭も骨も大きいですが、それしか食べられる部分がないんだ、というのは新鮮な驚きでした。品種改良で肉厚にするというのは、ひとつの解決方法になりますよね。食糧危機やフードロスや安全性の問題を考えたとき、天然ものだけでなく養殖も含めた多方面な選択肢を考えられるといいですね。子どもたちがずっとおいしく魚を食べ続けられる世界を守るためにも、学び続けることが大切だなと感じています」
「名もなき魚」との出会いに惹かれて
「魚をもっとおいしく食べてほしい」と、何度も繰り返し口にする和田さん。魚を取り巻く未来は、どんなところから変わっていくだろうか?

「世の中には、その地域でしか獲れなくて流通に乗らない “名もなき魚”が、たくさんあると思うんです。流通から弾かれて捨てられてしまう理由は、サイズや食べやすさ、味などいろいろあると思いますが、そういう魚もぜひ食べてみたいです。だって、いろいろな魚が食べられるのは、海に囲まれた日本だからこそ味わえる贅沢だから」
例えば地方の寿司屋で、聞いたこともない地元の魚のネタが出てくると、思わずワクワクしてしまう。
「そんな見たことも聞いたこともない魚との出会いをもっと楽しむことが、海のこと、水産業のことを身近に考えるきっかけになるんじゃないかなと思っています」
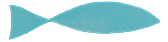
和田明日香さんの考える、魚のおいしい未来
一家に一台、生け簀があったら面白いですよね。今日はこの魚を食べようと目の前で選んで、そのまま調理して食べる。そんな未来があったら楽しいな。食べること、生きることが、身近な体験としてつながっていきそうですよね。家では無理でも、せめてスーパーには生け簀があるのが当たり前。その中にいろんな魚が泳いでいる。そんな未来になってくれたらうれしいですね。
料理写真(3点)/『楽ありゃ苦もある地味ごはん。』(主婦の友社)より

和田明日香
和田誠さんと平野レミさん夫妻の次男と結婚。結婚当初はほとんど料理の知識がなかったものの、修業を重ね食育インストラクターの資格を取得。現在は3児の母として、家庭と仕事を両立する。料理家としての活動のほか、テレビ出演やラジオパーソナリティー、食育関連の講演会やトークショーなどさまざまな分野で活躍。