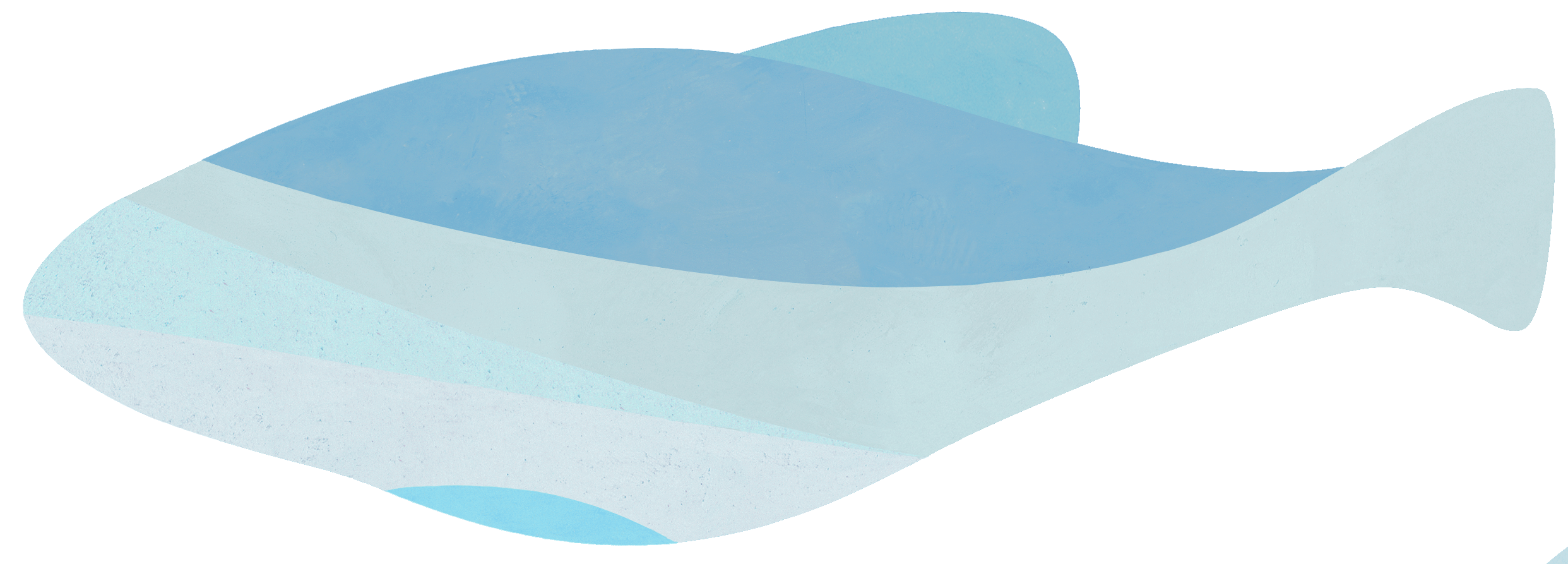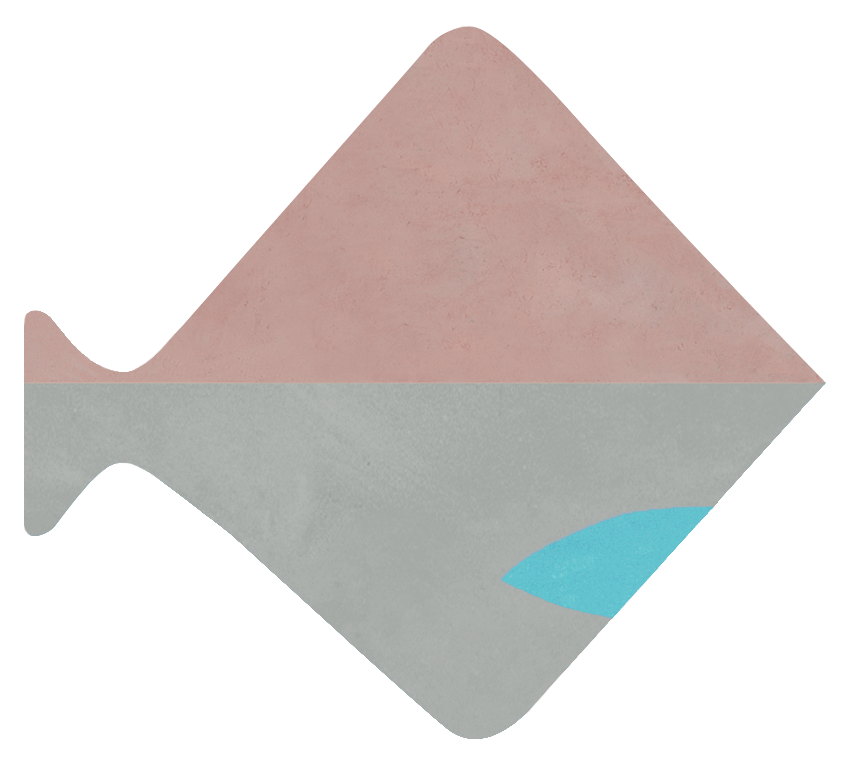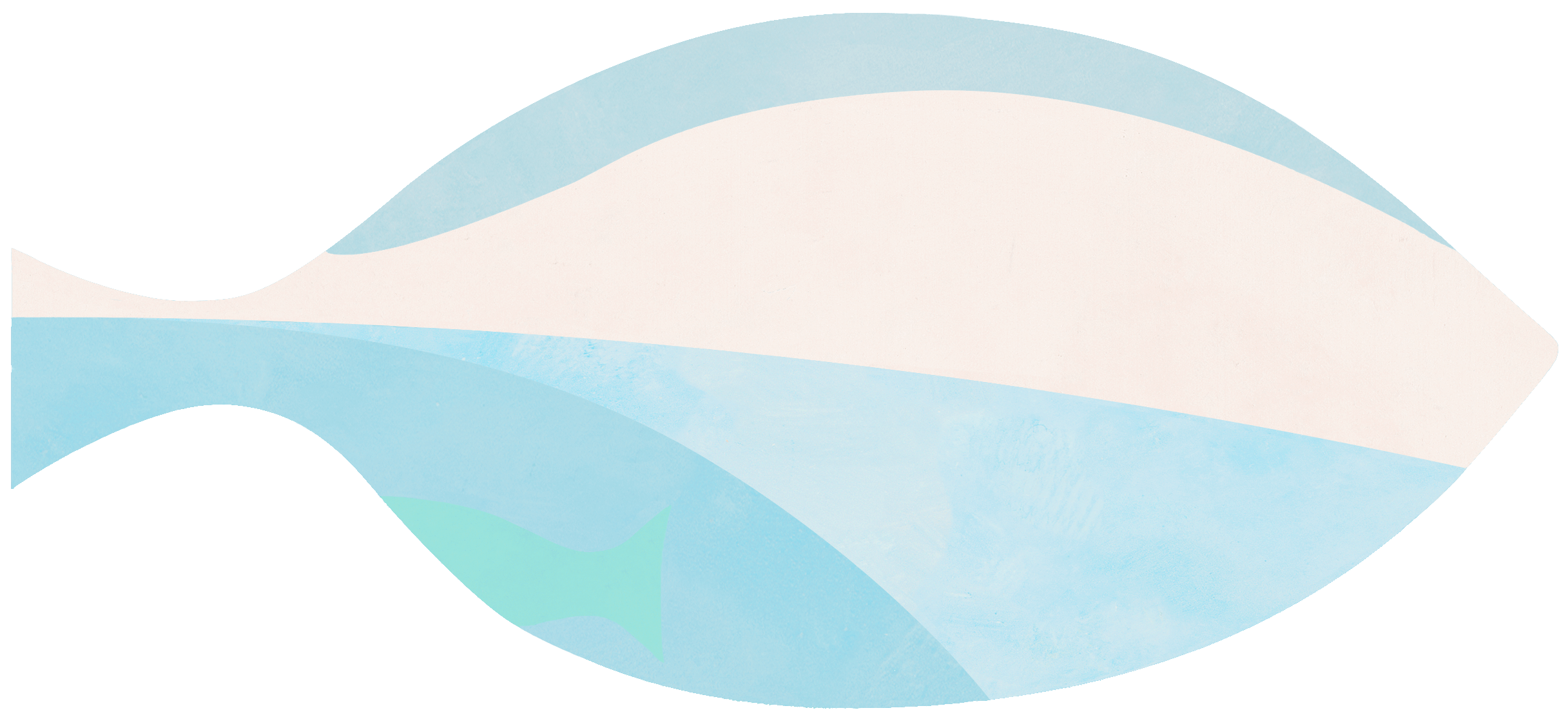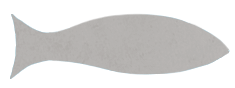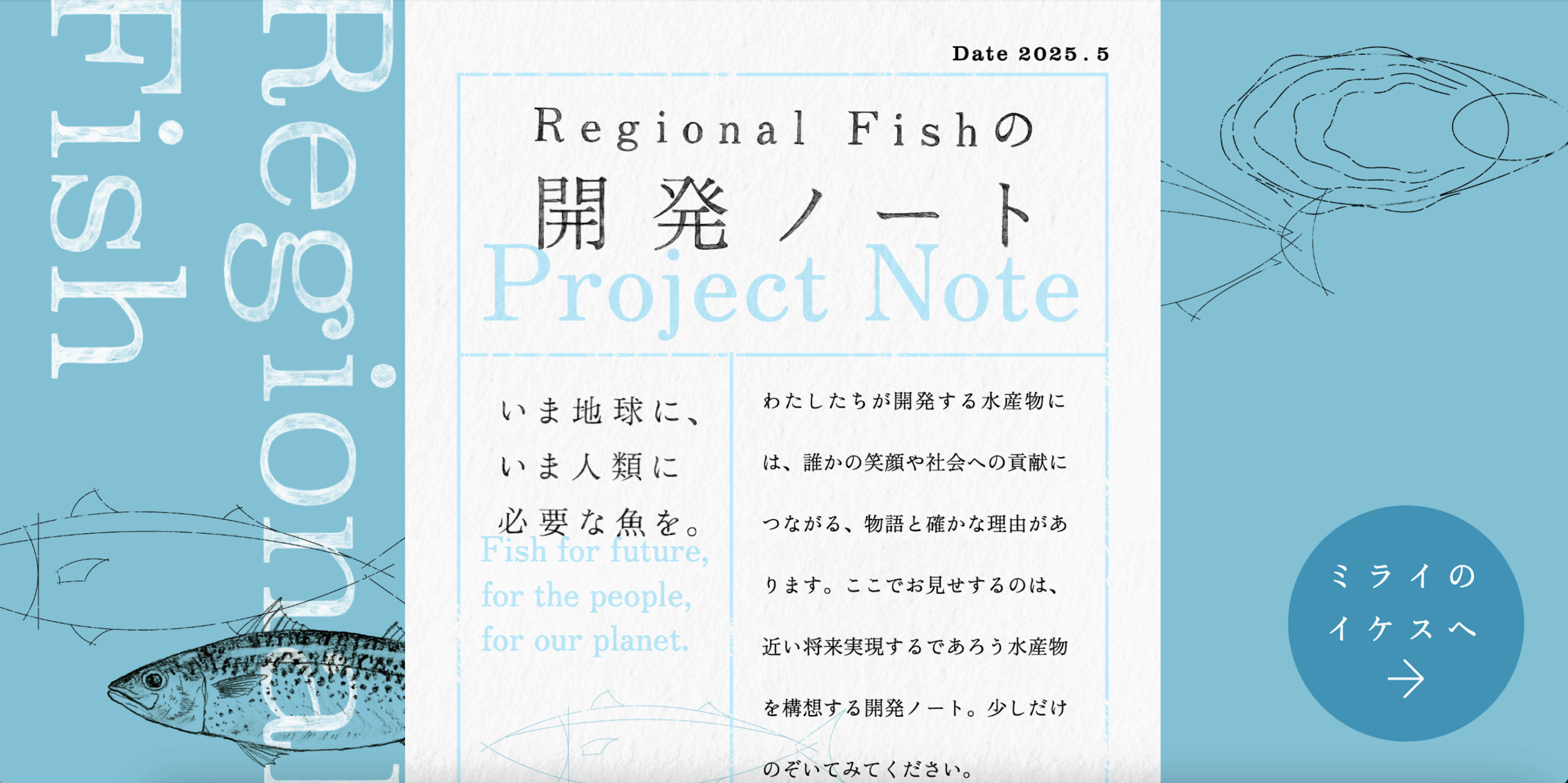「魚は天然物がいい」が寿司文化を壊すかもしれない

梅川さん:日本の漁獲量は、ピーク時の3分の1にまで落ち込んでいます。その背景には、海水温の上昇や漁業従事者の高齢化など、漁獲環境の変化があります。一方で家庭での消費を見てみると、魚の価格が上昇し、また価格と食べやすさ・調理のしやすさを理由に食卓には家畜の肉が増えていることから“魚離れ”も進んでいます。
これからの時代、どんな魚があったら、日本の食卓に魚を残していけるのか。そして魚食や日本の食文化を未来につなげるにはどうすればいいのか−−。日本料理界を牽引する村田さんと一緒に、考えてみたいと思います。
村田さん:これはほんまに、料理人と研究者が一緒になって考えていかなあかん問題やと思います。料理人のなかには「天然物しか使わない」という人もいます。でもその結果、どうなっていますか? 天然物の取り合いで値段はどんどん上がって、東京の寿司店や割烹店のおまかせコースは、いまや7万円、10万円なんてのも珍しくない。普通に考えて、まぐろの寿司2貫で1万5000円なんて、おかしいと思いませんか?
こういう“おかしなもの”は、必ず時代に淘汰されていきます。僕は、このままでは江戸の寿司文化そのものが消えてしまうんちゃうかと、本気で心配しています。

梅川さん:野菜や果物、肉については、「天然物がいい」と言う人は、ほぼいないと思います。そもそも、いま私たちが口にしている農作物・畜産物のほとんどは、長い時間をかけて品種改良されてきたものです。たとえば、固くて食べられる部分の少ない野生のイノシシは、肉質がやわらかく食べる部分が多い豚となり、小さくて苦味の強い野生種の植物は、食べられる部分が大きくて苦味が少ない食べやすい野菜や果物へと進化してきました。
そうやって人類は、おいしくて育てやすい作物や家畜をつくり、食文化を発展させてきたんです。魚だけが天然でなければいけないというのは、ある意味でとても不自然な考え方だと思います。
村田さん:天然のほうがうまい、とも一概には言えません。脂がしっかり乗った、とろけるような口当たりを求めるなら、養殖のほうが優れていることもある。それに、料理人の立場からいえば、食べる人が「おいしい」と喜んでくれるものを安定した価格で届けることも大事です。
天然物にこだわって値段が3倍になるくらいなら、味わいに遜色のない養殖魚を、きちんと素材に合った調理で提供するほうが、よほどええと思います。
伝承すべき技は…ない!? 新しい挑戦の連なりが伝統をつくる
梅川さん:格式高い「菊乃井」のご主人である村田さんが、品種改良や養殖にも積極的なご意見をお持ちであることに、うれしさと同時に驚きも感じています。
村田さん:「日本料理の技の伝承」なんて言いますけれど、伝承すべき技なんて、ないんですよ(笑)。たとえば大根。江戸時代の大根といまの大根はまったくの別物です。昔やったら、大根は米のとぎ汁でゆがいて、水でさらして、それを追い鰹して出汁で煮含めていた。でも、いまの大根でそれをやったら、“出汁の立方体”になりますよ。大根の持ち味が全部消えて、大根なのかカブなのかもわからんようになる。
梅川さん:つまり、食材の変化に合わせて、料理の手法も変えていかなければならない、と。

村田さん:その通りです。素材が変わり、食べる人の嗜好も変わっている。江戸時代の人は、イタリア料理もフランス料理も知りませんよね。味覚も文化も変わっているのに、料理法だけを伝承するなんてナンセンス。むしろ、伝統を守ろうと思ったら、常に新しいことをやり続けないとダメです。
振り返ったとき、そのひとつひとつの挑戦が線としてつながっていれば、それが伝統。だから、リージョナルフィッシュさんが取り組む品種改良や養殖も、必ず100年後には食の伝統のひとつになっていくと思います。

「菊乃井」のだしは、京都大学のラボと共同研究により、旨み成分であるグルタミン酸やイノシン酸の抽出量を測定・検証する実験を重ね、最適な時間と温度による抽出方法を導きだした。
真の「地魚」が生まれるとき
梅川さん:お話を伺って、ますます僕たちが手がける品種改良には、新しい伝統をつくる可能性があると確信しました。たとえば、僕たちはエサの量が少なくて良く、かつ成長スピードの1.9倍速いトラフグの品種改良に成功していて、いまは毒のないフグの開発を進めているところです。これが実現すれば、これまで食べられなかったフグの肝まで食べられるようになります*。そうなれば、フグの肝を使った新しい料理がきっと生まれてくるはずです。
*フグの内臓(肝臓・卵巣・腸など)には、まれに致命的な毒素テトロドトキシンが含まれることがある。そのため、フグの有毒部位の販売・提供・調理が食品衛生法により禁止されており、処理には都道府県認定の「ふぐ処理者」資格が必要とされている。

村田さん:それは、ええですね。フグはもともと内臓の大きい魚ですから、肝まで食べられるようになったら、食材としての価値はさらに上がると思います。しかも、フグは癖がなくて食べやすいし、世界中の海にいて、養殖にも向いている。世界的に見れば人口が増える一方で、タンパク源が足りなくなっていくなかでは、フグは地球の食の未来をより良くするまさに「EARTH FOOD」*やと思いますよ。でもいまは、フグの肝を出したら営業停止になりますからね。そういう意味では、法律も時代に合わせて変えていかないと。
*「EARTH FOODS 25」は、2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」と食業界の有識者たちが選定した、世界に共有したい日本発の食材、食品、食の知恵・技術の25のリスト。村田さんは検討委員を務めた。
梅川さん:一方で、自然でしか確保できない魚もたくさんいます。たとえば伊勢海老は成長速度が遅く、ズワイガニは深海の環境を再現できないので、人間が養殖することは難しい。そういう魚介類については、海そのものを回復させるアプローチが必要でしょう。マダイやマグロ、ウニ、フグ、海藻類など、養殖が可能な魚介類は、今後ますますニーズに合わせて品種が変わっていくはずです。たとえば、マダイの中でも「脂質が多いもの」「旨みが強いもの」「食べられる部分が多いもの」など、求められる特性に合わせて品種改良し、それぞれの地域や海の環境に合った品種が生まれる可能性だってあります。

村田さん:以前、青果のプロに「どんな野菜でもつくります」と言われたことがあります。トマトは完熟しても割れないように皮を厚くして、きゅうりは苦味やえぐみをなくした。料理人のニーズに合わせて、どんな改良でもするから言ってくれ、と。
梅川さん:福岡の「あまおう」と栃木の「とちおとめ」は、どちらもイチゴですが、産地だけでなく品種そのものが異なり、それぞれの地域の特産になっています。同じように「瀬戸内で育てたマダイ」と「三陸で育てたマダイ」が、それぞれ異なる特性を持った別の品種になっていけば、それこそ真の意味での“地魚”になる。地域の文化や産業、魅力にもつながっていくと信じています。
いまこそ、研究者と料理人が手を取り合うとき
村田さん:50年後には日本の人口は7000万人になると予測されています。高齢化が進み、経済発展も国際競争力も期待できない――そんな時代がやってくるんです。日本はアジアでも有数の“貧乏国”になってしまうかもしれない。そうなったとき、日本の子どもたちを飢えさせないためには、いま何をすべきか? やっぱり、50年先の未来を見据えた行動が、いま必要なんやと思います。

梅川さん:現時点でも、食料自給率は40%弱、エネルギー自給率は13%ですからね。50年後はかなり厳しい数字になっているでしょう。
村田さん:そう考えると、魚というのはますます重要なタンパク源になります。日本の海岸線の長さは、なんとアメリカの3倍。国土は小さくても、海岸線は世界で6番目に長いんですよ。この海の力を活かさずして、未来の食を守ることはできない、と思います。この海で獲れる魚をもっと大きく、もっとタンパク質が摂れるようにしていく。海藻もタンパク質が豊かですが、魚と同様に生育しにくくなっていますね。海藻も、海の変化に合わせて、適応できる養殖場をつくる。そういう運動こそがいま必要で、それを研究者のみなさんと一緒に考え、行動していくことも、料理人の責務やろうと思うんです。
手遅れになる前に!未来を生きる子どもたちのためにできること
梅川さん:魚の交配を繰り返すことで少しずつゲノムを変えるため、従来は20〜30年かかっていた品種改良が、現在ではゲノムを安価に読むことも変えることもできるようになったので、ゲノム編集技術を使えば2〜3年で品種を改良することが可能です。イノシシを家畜化して豚にしたときには、成長速度を2倍以上にアップさせ、顔は小さく、肋骨は2対伸びて胴体を長い形質に変えることで食べられる部分を増やしました。同じように、魚においても、身を大きくしたり、成長スピードを早めたりといった改良が可能です。また、海水温が高くても生きられる、高温耐性を持つ魚の開発も進めています。

村田さん:ゲノム編集や品種改良という言葉を聞くと、なんとなく怖いって感じる人も多いでしょう。でも、怖がるばかりではダメですよね。そうやって「怖い」「嫌や」と言えるうちはまだええんですよ。ほんまに問題なのは、生産者も漁業者もいなくなって、いざ食べるものがなくなったときに「どうしよう?」ってなることやと思います。
梅川さん:もはや遠い未来の話ではありませんね。
村田さん:それに、「海水温が上がって漁獲量が減った」とか「海藻が全滅した」とか、課題を並べるだけでは何も変わらない。ちゃんと科学的な裏付けに基づいて、行動を起こしていかなあかんのです。たとえば、産卵期には禁漁期間を設けるとか、需要の多い魚介類は獲りすぎを防ぐために、陸上養殖施設を整備するとか。そういう「未来につながる仕組み」を考えて、実現のために資金を集めたり、協力者を募ったりしていかないと、前に進まないでしょう。
料理人とつくる「理想の魚」とは?

肉厚の伝助穴子をすり身にし、なめらかな豆腐寄せに仕立てた「穴子豆腐」。みずみずしい冬瓜と山椒の香りが、涼やかな風情を添える。
梅川さん:村田さんは、品種改良でどんな魚ができたらいいな、とお考えになりますか?
村田さん:京料理には、白身の魚が不可欠なんです。だけど、どんな魚をおいしいと思うかというのは、やっぱり地域によっても違いますね。関東の人は脂身の多いトロや赤身が好きで、関西の人は毎日食べても飽きのこない、淡白な白身が好む傾向がある。そういう地域ごとの嗜好は、思っている以上に大きいと感じます。
梅川さん:地域に合わせて、脂のノリを変えていくのも、ひとつの品種改良の方向ですね。
村田さん:それは大いにあるやろうね。魚にも“地域に合った味”や“料理に合った味”があります。京料理、寿司、イタリアンでは、それぞれ求められる魚の性質が違います。だからこそ、品種改良によって“どう食べたいか”に合わせて魚を選べるようになれば、それはすごくええことやと思います。

梅川:アレルゲンのないエビ、アニサキスが寄生しないサバなども、現在研究段階です。小骨が少なく、調理しやすい鱧もできると思います。実現すれば、より気軽に、より安心して魚介類を楽しめる未来がやってくる。
村田:たとえば鰻でも鱧でも、あの細長い体型じゃなくて、もっと短くて太い魚体のものができたら、身も厚くて脂ものって、食べる人は喜ぶかもしれない。そういうふうに料理人と一緒に“理想の魚”を考えていく時代になっていくかもしれませんね。
梅川:そうですね。養殖できる魚は、もっともっと変われると思います。
村田:そして何よりは、おいしいことでしょう。おいしいことは、正義なんですよ。
梅川:今日いただいた穴子豆腐は、僕の人生でいちばんおいしい豆腐でした! 村田さん、ありがとうございました。

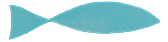
村田吉弘さんの考える、魚のおいしい未来
和食は、出汁の旨みを中心に構成される料理です。その旨みを支えるのが、昆布や鰹節。けれどいま、海水温の上昇や海の栄養不足などによって、昆布の生息地が激減しています。僕は、「OCEAN PLANT」というプラットフォームを立ち上げ、日本の海岸線を良質な藻場に変えていく取り組みを始めました。また、昆布以外の海藻類からも、旨み成分であるグルタミン酸が抽出できれば、新しい出汁ができるかもしれない。ひとつの食材だけに頼り、「これがないからつくれない」というのではいけません。養殖や品種改良も含め、新しい可能性を探し、考え続けていくこと。それが、魚のおいしい未来につながっていくんちゃうかなと思います。
梅川忠典さんの考える、魚のおいしい未来
たとえば豚肉は、ラード用とベーコン用で豚の品種が異なります。同じように魚も、料理や用途に応じて品種を多様化していけると考えています。身が太いもの、DHAを豊富に含むものなど、特色のある魚がそれぞれの地域で育てられるようになれば、地域の名産品が生まれて、その地域の水産業にも新たな活気が生まれるはずです。やがては、日本各地や世界から、「その土地でこそ食べたい」と人々が訪れる、ガストロノミーツーリズムの立役者になるかもしれません。
魚は「ローカル(地方)」の食材を超えて、「リージョナル(地域)」の顔となる存在へ。そんな未来を、ゲノム編集やスマート養殖を通して、地域と一緒に育てていきたいと思っています。

村田吉弘
1951年、京都府京都市生まれ。立命館大学在学中にはフランス料理研究のため半年間渡仏する。1976年に「菊乃井」に入店し、93年に父の跡を継いで「菊乃井」3代目主人となる。2004年に東京へ「赤坂 菊乃井」を開店。「菊乃井本店」はミシュランガイド京都・大阪にて、16年連続で三つ星の評価を得ている。

梅川忠典
京都大学大学院を修了後、デロイトトーマツコンサルティング株式会社にて経営コンサルティング業務に従事した後、 株式会社産業革新機構にて大手・中堅企業へのバイアウト投資および投資先の経営支援を担当。 2019年4月にリージョナルフィッシュ株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。NTTとの合弁会社であるNTTグリーン&フード株式会社の取締役CSOを兼任。